冬の時代
【――】 そのくらいの時期から、現在の第3次ブームになる間の状況というのは、どんなものだったでしょうか。
【堀】 アメリカではAIからぱっと人がいなくなったんですが、日本はしつこくこつこつやり続けていたんですよね。
【――】 ちょうどその時代に、堀先生は人工知能学会の会長を務められていたわけですね。
【堀】 そうですね。2008年から2010年ですね。そのときは、冬の時代が、あ、終わったなという印象でしたね。
冬の時代には、「人工知能学会なんてまだあるの?」とか言われたり、人工知能学会の理事会でも名前を変えたらどうかという理事がいらっしゃったりですね。議論したことはありますが、変えなくてよかったなと、今は思っています。
そのAI冬の時代も基礎研究はずーっと続いていて、発想支援系でも、実際にいろんな工学的な設計に応用するという仕事がこつこつ続いていた。僕は先端研所属で、教育は航空宇宙工学と組む形になっていましたので、航空の人工衛星のミッション設計とか、飛行機の設計とかにも使ってもらうというのをやっていましたし。
あと、宇宙工学というのは、実は人工知能の応用としては不可欠の領域で、探査機が宇宙に行くと、通信時間がかかってもう地上から遠隔操作がリアルタイムでできませんし、壊れても修理に行けないので、自律的に修理してほしいということで、機械の自律化という意味では、宇宙というのは非常にいい応用ができる。そういう意味で、自律システムというのも引き続き、二本柱のひとつとして僕はやり続けていましたね。それには、人間の代替というよりも機械がとにかく自分で賢く仕事をしなきゃしょうがないという現実的な要請もあった。
あまり目立たないけれども、応用にしろ基礎にしろ、ずっと引き続きやっていたという形ではありました。
【――】 そういう意味では、堀先生ご自身としては、発想支援を核として、研究はずっと同じ前提でされてきたと。
【堀】 そうなんですね。基本的にはそうですね。そういうことになると思います。
そういう工学的な領域における発想支援の応用だけじゃなくて、発想支援というのはおもしろいとおっしゃってくださる仲間が広がって、多摩美の須永先生というアート系の先生とか、それから、東大の情報学環の水越伸先生というメディア論の先生などと一緒にCRESTのプロジェクトをやって、一般市民の方が創造的な活動をしたいという潜在的な欲望を持っているんだけれども、絵を描いたり詩をつくったりというのはなかなか敷居が高いと。そこにちょっとした支援とか、ワークショップのプログラムをうまく工夫すると、一般市民も創造活動を楽しめるんじゃないかというのをCRESTのプロジェクトでやるというところでも、別の領域での応用をやっていた。まだ第3次AIブームが起こる前です。
【――】 それはハード的なものもソフト的なものも全部含めた発想支援という感じなんですね。
【堀】 そうです。総合的なものですね。僕らの計算機システムは、陰でほんの小さな役割をするだけで、全体的なワークショップの設計だとかいうのを水越さんのグループだとか須永先生のグループだとかと一緒にやると。
【――】 堀先生ご自身の研究の位置づけとしても、一方で人工知能研究の1ジャンルでもあるけれども、他方では、発想支援という技術の1つとして、人工知能を使った発想支援があるという側面もあるという感じでしょうかね。
【堀】 はい、そういうことになりますね。
【――】 そういう意味では、教育学が状況とか環境とかについて考えるというのは、かなり親和性が高いと。
【堀】 ええ、まさにそうです。
それで、うちの研究室は、学生がとにかく好きなことをやるというのを基本方針にしていて、僕の専門と関係なく何でもいいからやるというのをやっているんですね。やっていると何となくつながっていく。今おっしゃった教育も、小学校の教育支援をやりたいというので、通常の支援AIじゃなくて、学習支援でね、子供たちが勝手にいろんなことを試して何か発見するようなことをやっていた。今はそういう環境型の学習支援というものが主流ですけれども、それのちょうど出始め。
うちの学生がそういうのをやりたいというので、実際に小学校に自分がつくったツールを持ち込んで、子供たちがツールを、いわば文房具がわりに使いながら何かを発見する。それまで教室でおとなしかった子が、急に元気になるというので、先生に喜んでもらったり。
そのときも佐伯先生などにもアドバイスをいただきながらやっていた。だから、その学生はうちの研究室の所属ですけれども、佐伯研のゼミにも出ていました。その学生は、航空の学生ではなくて、先端研の先端学際工学専攻という社会人中心の専攻だったんです。
あるいは、変わったところでは、これは比較的最近なんですが、アフリカ大好きという学生がいてですね、アフリカのような新興国で、新興国の人たちが自分たちのための技術開発をすると。そうすると、先進国でつくるものとは違う発想でおもしろいものができるというのをやりたいといって、実際にガーナに長期間滞在して、半年ぐらい滞在して、ガーナの工業高校の学生、先生たちと一緒に新しいものを設計する、その支援システムをつくる。そのときにも、結果的には発想支援の技術も取り入れるということが行われました。
なので、発想支援にこだわりがあるというよりは、何か人々が今までより楽しく、より創造的に仕事をするための道具や環境、仕組みというのをいろいろ考えて試してきたというのが、一つ大きな流れだと思います。
【――】 その中で、例えば、佐伯先生のグループがやっているようなある程度理論的な話というのは、それが先にあってやっているというよりは、むしろ実際に現場で問題解決に取り組んでいたら、結果的にちょうどそれに合うような議論をやっている人もいたということなんですね。
【堀】 まさにそうですね。
【――】 ある意味で、実は違う方向から同じ問題にアプローチしている人が見つかるという感じなんですね。
【堀】 そうですね。佐伯先生の認知科学も、議論だけ、空論をやっちゃだめだという立場ではありますよね。実世界での人々の認知行動、認知活動というところから理論を組み立てる必要があるという立場。そういう意味では、非常に基盤は共通しているということです。
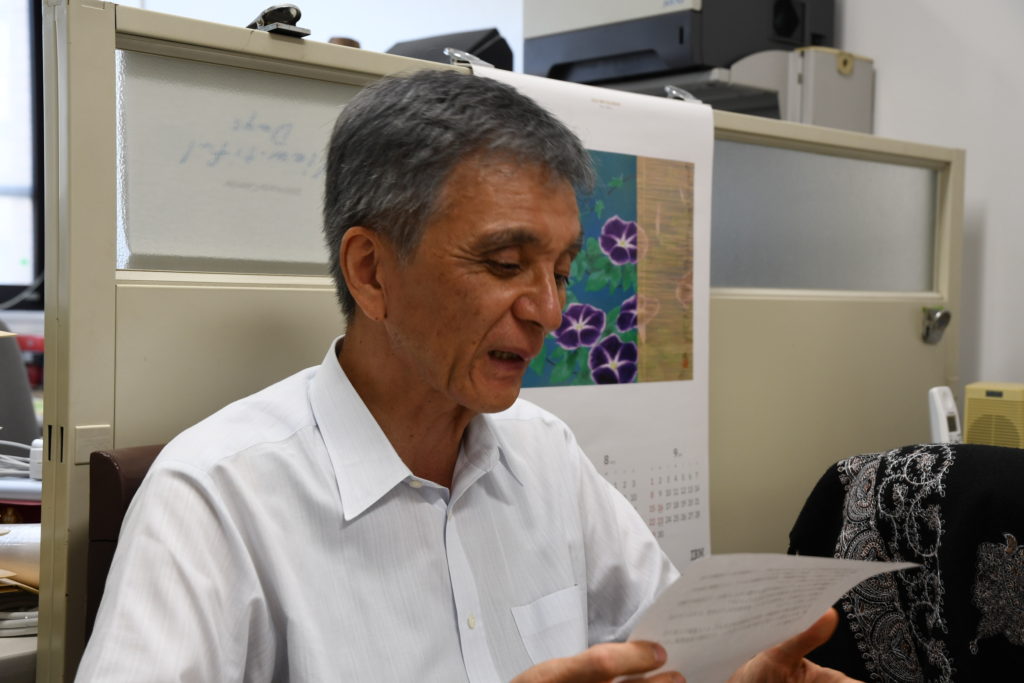
第2次人工知能ブームの教訓
【――】 また少し昔の話に戻りますが、第2次人工知能ブームのときの理論的な話で、特に重要だったと思われる論点、問題がもしあればお聞かせください。
【堀】 当時哲学の先生と一緒になって一番議論したのは、知能の基本メカニズムにおける記号の役割。記号処理というのがどれくらいのものなんだろうと。僕らはとりあえず記号処理でやれるところまでやってみて、当然やれないところは残るだろうという立場でやっていたんですよね。
それで、やっぱりわかんないのは、記号をどうやってつくるとか、記号はどこから生まれるかということ。ニューラルネットのモデルはずっと昔からあるわけで、じゃあニューラルネットでいいのかというと、当時のニューラルネットでいいとも思えなかったんですよね。やっぱり力不足で。
ちょっと話が現在に飛んじゃいますが、力づくでやると、かなりの部分、当時は無理だと思っていたことは結構やれるんだなというのが、第3次AIブームの現在の状況だと思います。
それで、当時は、コネクショニストと記号主義者というのは激しく対立していました。第3次AIブームがうれしいのは、そこがつながり始めるかもしれない、つながりそうだなというところがうれしい。
当時から土屋さんとかは変わらず計算主義者で、知能というのは計算でいいんだ、計算で表現できるものをもって知能といっていいんだという計算主義の立場だったと思うんです。それで、ゼノン・ピリシンとかもばりばりの計算主義者で、計算で全てを言えると。
僕ら人工知能屋は、計算、記号処理でやってはいるんだけど、やっぱり自分でやっているから限界はわかっているわけですよね。記号処理だけではどうしてもうまくいかない。そこで、記号をどうやってつくろうかというところが問題になって、僕自身は発想支援とかをやっていたんですよね。
土屋さんとかは、ポランニーとかに対しては冷たくて、あれはバックグラウンドの議論で、哲学のフォアグラウンドの議論じゃないとかいうおっしゃり方だったと思う。でも、僕なんかはそのバックグラウンドとフォアグラウンドがつながるところに興味があった。それで、野家先生とかから教えていただいたフッサールの現象学みたいなのは、現在生きている海の上に浮かぶ船としての知能、周りの世界と自分とのかかわりの中でしか知能を議論できないという説明だった。ああ、それはまさに僕がやりたいことそのものだということで、当時としては非常に刺激になった。現象学そのものはちゃんと勉強したわけではないけど、ああ、すごく気になるな、おもしろいなと思って。
あと、ハイデガーを議論して、ハイデガーの道具とは何かとかいう、世界内存在とかいう、僕らは全然理解できていないんだけど、そういうテクニカルタームにはすごく興味があって、じゃあAIにとって外界にあるものと自分とのかかわりというのをどう実現していくんだろうと。
当時の記号処理だけでは、明らかに世界と自分とのかかわりというのは扱えなかったんですよね。その中で状況意味論とか状況理論というのがアメリカのスタンフォードの連中から生まれて、我々としては、状況意味論というのは、僕らが一番知りたかった状況とエージェントとのかかわりというので、これいいかもしれないといって、一時期わっとみんな飛びついたんですよね。
僕自身も最初、わりと一生懸命バーワイズとペリーの本とか読んだんですが、だんだん彼らは完全に数学の世界に入っていって、当初興味を持っていた世界とエージェントとのかかわりみたいなところからは離れていった印象がある。土屋さんはずっと状況理論の連中と一緒に数学的な基礎理論のところにもつき合っていましたね。
【――】 そのあたりの話は、先ほどのエキスパートシステムのところでも出てきましが、人間の知識なり知能なりというのは、明確に言語化できる部分とそうでない部分があって、そのそうでない部分というのが何なのかというのがやはりかなり大きな関心だったと。
【堀】 ええ、ですね。土屋さんは、知能だけの計算を書くだけじゃなくて、この体の外にある世界も含めて全部書きゃあいいんだという立場だったんです。状況理論の人たちはそうで、全部書きゃあいいんだ、でも、書こうとしたのにやっぱり書けなかったというのが最後だといっていいのかな。まあそうなんじゃないでしょうかね。
【――】 そういう意味では、明確に記号化できる部分とそうでない部分が何となくあるんではないかという感覚はずっと持たれていたと。
【堀】 そうですね。
【――】 明確に記号化できないようなところを、じゃあどういうアプローチで捉えたらいいのか。
【堀】 僕はやっぱり計算系ですから、記号で書けなかったところも、書けるものは書いて使えるんだったら、それはそれでうれしいんですよね。だから、書けないといってそこで捨てちゃうんじゃなくて、とにかくつなぎたいと思う。それで、つなぎ方はいろいろあってもいいんじゃないかなという立場です。
ですので、第2次人工知能ブームから冬の時代にかけて話題になった、状況依存性だとか、あと身体知ですね。体の果たす役割ですね。それで、心身問題とかでまた哲学の人たちと一緒に議論する。体の果たす役割とか、それからこれは松原さんが一番好きだったフレーム問題とか、情報の部分性だとか。そのあたりの、空中に浮かんだ知能ではない、世の中で生活する実体としての知能、そのときに何がどう起こっているのかということを知りたい。これは、ずっと人工知能と哲学の先生で議論しながら、まだ答えは出ていないと言っていいと思うんですが。
【――】 そうですね。
【堀】 そのあたりはAIだけでもだめだし、今後は哲学だけでもよくないので、一緒に引き続きずっと、基礎的な学問領域としてやり続ける領域だと思うんです。
【――】 ただ、哲学者は、じゃあ技術的にどう落とし込めるかというときに代替案を出してくれるわけではないですね。
【堀】 ええ。それはまあ、答えがなくていいんだから、一緒に議論を楽しむ知的領域としてずっと生き続ければいいんじゃないかなと思います。
【――】 哲学的な概念は、そのままだと、人工知能研究にどう落とし込んだらいいのか、そこまで結びつけるのはやはり難しいですか?
【堀】 やれば何かできそうですね、またね。しばらくまだやっていなかったですけどね。
【――】 認知科学の哲学でも、さきほどおっしゃられた状況性とか環境性とか身体性とか、それらをある程度考えずにはやれないという考え方、身体性認知科学という言葉も出てきています。認知や心について考えるときには、当時指摘されていたもやもやした部分も無視できないという雰囲気は、完全にできているように思われます。
【堀】 そうですね、そう思います。だから、人工知能を当時からやっている人たちは、認知科学者や哲学者と、その問題意識を完全に共有しているんですよね。
今入ってくる若い人工知能研究者には、そこを全く無視している人も少なくないので、もう一度そこの根本的なところをやるのは、学問領域としては非常に重要で、第3次人工知能ブームが落ちついたときにまた盛り上がってくるんじゃないかな。